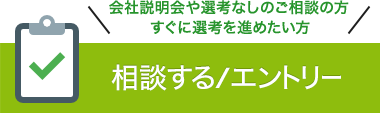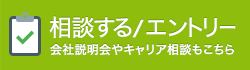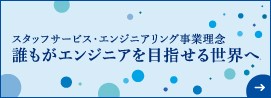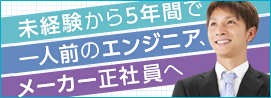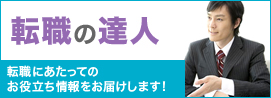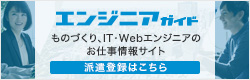メールでスキルアップ相談「そうだんくん」Q&A紹介
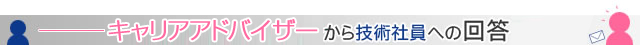
Q34. CADオペレーション及びモデリングについて教えてください。
現在UNIGRAPHICS NX5 を使って重機のモデリング及び組み立図等を作成しております。設計変更が容易に出来、誰が見ても解りやすいモデリングを目標に勉強をしたいと日々感じております。
(1)オペレーションにおいては就業先のマニュアルやオンラインマニュアルを参考に作業をしてきましたが、理解するのに時間がかかってしまいます(力量不足だと思いますが何とかしたい)。市販のオペレーションマニュアル・webサイト・教育システム等なかなか見つかりません。分かりやすい書籍やWebサイトなどを紹介してください。
(2)設計変更が用意に出来き、誰が見ても解りやすいモデリングはどの3DCADも同じなのでしょうか?

重機メーカー就業中の方より
A34.ご相談にお答えします。
回答①:キャリアアドバイザーからのアドバイス
私は自動車メーカーで3次元CADを使用した機械設計を11年間やっておりましたので、専門分野ということで今回ご相談に回答させていただきます。
【ご相談内容】
設計変更が容易にでき、誰が見てもわかり易いモデリングを目標に勉強したい・就業先にあるマニュアル以外に市販でわかり易い書籍なりwebサイトがないか?
・誰が見てもわかり易いモデリングはどの3DCADでも同じか?勉強方法は?
【 回 答 】
着目点が大変よいですね。早速回答していきます。3次元CADモデリングでは「コマンドや機能などが操作できること」が重要ではなく、
①設計基準を明確にする
②1つのフィーチャーは1つの設計機能に対応させる
③重要な機能から順に設計する
など「設計のプロセス」を考えたモデリングをすることが重要になってきます。これはNX5に限らず他の3次元CADでも基本的に同じです。
設計プロセスを考えたモデリングの例ですが、下図の様な3つの段差がある多機能(多目的)シャフトをモデリングする場合、
○…各々のシャフトの機能を考え一つひとつの要素ごとに形状を作っていく
×…シャフト断面を描いて、あたかも一つの機能のようにまとめて設計してしまうと、そのうちいくつかの要素に修正を加えようとした場合に修正できないか、修正できたとしても別の要素に影響を与えてしまいます。
この様な設計プロセスを重視したモデリングのコツがまとめられている書籍をご紹介します。これを見ると「設計変更が容易にでき、誰が見てもわかり易いモデリング」のポイントが分かり参考になると思います。
【紹介書籍】
・3次元CAD活用設計再入門 出版:日刊工業新聞社 \1995
この他にも設計者としてのノウハウを身に付けることができれば、モデリングをする際にも役に立ちます。設計者としてのノウハウの一つとして、寸法の記入一つで部品のバラツキが変わる(下図参照)ということがあります。また、部品の加工手順や材料の特性(強度や比重等)などについても理解していないといけないということです。
CADが勝手に設計してくれるわけではないですから設計する上でのコツやノウハウをもって設計者としてCADを操らないといけません。
ですから、CADの操作習得と併せて「設計的考え方のできるスキル」をこれから身に付けていきましょう。「設計的考え方のできるスキル」を身に付ける手順を下記に示します。
●「設計的考え方のできるスキル」を身に付ける手順
1、機械設計の基礎でもある「機械製図」を習得
↓
2、「機械工学の基礎」を習得
↓
3、「材料力学」を習得
↓
4、 品質工学、プレス加工法、金属加工技術etc
という進め方でやっていくことをお勧めします。
尚、上記1~4は全て当社の通信教育講座から受講可能で、WEBテクニカルセンターの「スキルアップ関連」のページ内で詳細を確認することができます(申込み方法も記載しています)。
やることはまだまだ沢山ありますが一歩一歩着実にモノにしていって下さい。
回答②:技術社員の方からのアドバイス
「Q34」で質問された方に、私からも本を紹介したいのでメールしました。
私は 自動車メーカーで6年、トレース・設計補助、産業機械メーカーで6年、設計や品質管理、また、化学系の企業で1年、実験装置の設計などを行ってきました。3D-CAD は現在勤務している自動車部品メーカーで、CATIA を1年使っている程度ですので詳しいテクニックはまだまだですが、設計の基本は同じだと思います。
キャリアアドバイザーの回答にあるとおり、重要な部位から設計をするのは大変重要な事と思います。それから、設計変更の可能性がある部位は、数値を後から変更できるように設定しておく事も大事だと思います。簡単な例で言えば、ブラケットなどは取り付け面を基準に板厚が変更できるようなスケッチを作っておけば後から簡単に変更できます。板厚が変われば曲げRも変わりますから、そこも後から変更できる形が必要です。慣れてきたら、数値が追従するように関数で設定しておくと楽になります。
尚、書籍ですが森北出版株式会社の「3次元CADから学ぶ機械設計入門」(\2,800) も参考になりますよ。