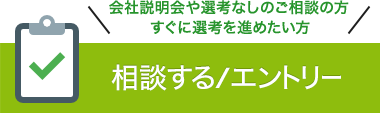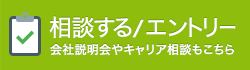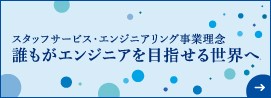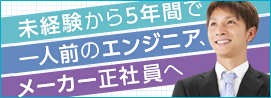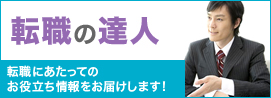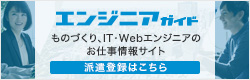メールでスキルアップ相談「そうだんくん」Q&A紹介
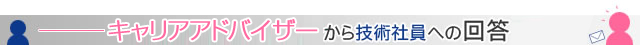
Q7. 「化学的に考える力」を身につけるにはどうしたらよいでしょうか?
まず、現在の就業先での私の理解力が追いつかないことが多々あり、その業務に対する理解度を上げるためにはどうしたらよいかを考えました。 その結果、「化学的にものを考える頭」が必要であるという結論に達しました(農業大学の畜産科を卒業しております)。よってその「考え方」に対するアドバイスをお願いしたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

化学系研究所就業中の方より
A7.ご相談にお答えします。
前職では、医薬関連など有機合成業務・高分子合成業務などの化学系の仕事に約30年間携わっておりました。製品の企画、文献調査から合成研究、サンプル作製および分析、解析、試作評価、量産導入と一通り経験しております。このような経験をもとにご相談にお答えします。
農学部畜産科のご出身ということなので、学生時代には化学系の勉強もされたことと思います。
ご承知のとおり、化学系の仕事は職場での上司からの指示を受けた時点で、ご自身がお持ちの化学系の経験、アイデアなどを総動員して、また、同部署の人たちとの討論や意見を確認した後に、安全を確認し、文献を調べたり、実験のモデルを考えたりすることから研究や実験がスタートします。化学的な考え方は、それらの仕事を遂行する経験のなかで醸成されていきます。
具体的には、下記が研究開発の流れです。
- 同僚のアイデアをよい意味で盗む(拝借する)
- 文献を調べる(会社の資料、図書の参考書から引用、文献検索でたとえば、会社で利用しているCASオンラインなどを使う)
- 安全を確認した上で、実験をしてみる
- その結果が出たら、また 1.~ 3.を繰り返して、なぜそうなったかを推理する(仮説を立てる)、そして、実証する
- 自信がついてきたら、人前でその調査~実験~仮説→結果、成果、今後の方針などをまとめて発表してみる
すなわち、化学では多くの科学がそうであるように、机上の空論では何の役にも立たず、仮説はあくまで、実証してからはじめて、化学として生きてきます。
そしてこの実証によって、会社の求める高分子材料の合成及び分析、医療材料の開発または細胞培養試験、ゲルの合成、などにおいて、有用性が出てくるのです。
ただ、こういった流れで作業を進めるにあたり、あせりは禁物です。
これからも、化学の道で生きていこうとされるのでしたら、試行錯誤や経験の積み重ねはかなり重要になってきます。また、なぜこうなるのか?といった自問自答を繰り返す、積極性が要求されてきます。
こういった考え方、仕事の進め方によって、ご質問の「科学的にものを考える頭」に自然となっていくと思ってください。なお、安全にはくれぐれもご用心くださいね。